横綱土俵入りをご存じですか?相撲取りの最高位である横綱が土俵に入る際に行う一連の所作で、一種の儀式・神事のことです。横綱しか許されていない型ですが実はこの土俵入り、肩甲骨や股関節の動きを整え・鍛える素晴らしい鍛錬法としての一面を持っているんです。この記事を読めば横綱土俵入りの見方が変わりますよ。さあ、横綱になった気分で土俵入りしましょう。
横綱土俵入りとは何か
横綱土俵入りとは、大相撲の最高位である横綱が本場所の幕内取組前や、
巡業先などで行う土俵入りのこと。
横綱の他に「露払い」と「太刀持ち」の二人を従えて行います。
関取が取組前に化粧まわしを着けて土俵あがるのは「土俵入り」と言い
「横綱土俵入り」とは区分されています。
今は両方とも顔見世などの意味合いが強いですが、いづれも元々は儀式・神事でした。
横綱土俵入りは神社などで奉納されていますよね。
横綱土俵入りには基本的な動作の流れがあります。
横綱土俵入りの基本的な動作
横綱土俵入りの基本的な動作は次のとおりです。
1 花道から入場する
2 土俵に上がる
3 拍手を打つ
4 土俵中央へ進む
5 拍手を打つ
6 四股を踏む
7 土俵の上がり口で拍手を打つ
8 一礼をして退場する
今回は5番の「拍手を打つ」から6番の「四股を踏む」までの動作を用いた
トレーニング方法を紹介します。
トレーニングとしての横綱土俵入り
トレーニングとしての横綱土俵入りの動作を紹介します。
拍手を打つ~四股を踏むの間を4つに分けます。
その4つとは
1 拍手を打つ
2 両手を広げる
3 四股を踏んでからせりあがる
4 左右の足で四股を踏む
です。
ひとつづつ説明します。
拍手を打つ
拍手を打ちます。
肩甲骨の動きを良くするトレーニングです。
大きく息を吸いながら両腕を頭上に上げます。
肩甲骨を大きく動かすような意識を持って回しながら上げましょう。
※膝は伸ばしたまま行います。適当な画像がありませんでした。
両腕は肘がやや曲がる程度に伸ばしたまま下ろして胸の前で拍手を打ちます。
拍手を打ったら両手を揉みます。
これは「塵手水」といって、所作の由来は「草木についた露で両手を清める」
ですので、それをイメージして手を揉みましょう。
塵手水が終わったら、再度、肩を大きく回しながら拍手を打ちます。
両腕を広げる
両腕を広げる動作です。
肩甲骨の動きを良くするトレーニングです。
拍手を打ち終わったら胸の前でパカッと両掌上向きに開きます。
掌を上向きにしたまま両腕を広げていきます。
この時に肩甲骨を寄せるようにするのが重要です。
両腕を広げたら左肘を曲げを左手を胸から脇腹あたりにつけます。
左手の形が整ったら右腕を横に伸ばしたまま右掌を返します。
今度は左手を伸ばし、右肘は曲げ右手を胸から脇腹あたりにつけます。
この時に右足を左足に寄せ、左腕を横に伸ばしたまま左掌を返します。
「両手を広げる」動作は以上です。
この中で左右の掌を返す動作がありました。
これは肩甲骨の動きにより体重移動をスムーズにする動作なんです。
文字上は「左掌・右掌」と表現していますが肩甲骨からグリッと回すようにしてください。
四股を踏んでからせりあがる
右足から四股を踏みます。
四股を踏み終わったら深く腰を割ります。
両手は「両手を左右に広げるか」「右手は広げてもう左手は肘を折り胸につける」
の2つの形があります。
これは土俵入りの型の違いで両手を広げるのが「不知火型」片手を胸につけるのが「雲龍型」です。
これは好みの型を選んでください。
ちなみに「不知火型」は攻撃の型、「雲龍型」は守りの型を言われています。
はっきりとした根拠はないそうですが。
深く腰を割ったところからせりあがります。
せりあがるときは足の親指を支点にして踵を内側に寄せます。
足を外旋させる動きですね。
踵を寄せ終わったら今度は踵を支点にしてつま先を正面に向けます。
この動きを5回ほど繰り返します。
親指の位置が徐々に内側になっていくにつれ足幅が狭くなりますから
必然的に姿勢が高くなります。
これが「せりあがり」です。
横綱土俵入りの動画などを見るとせり上がりの時に太ももを使って姿勢を高くするもの
もありますが、これは股関節のトレーニングとしてはもったいない。
膝の角度はなるべく保ったままで股関節の外旋を使うよう意識しましょう。
実際の土俵入りでも四股からのせりあがりは一番の見せ場となり、盛り上がる場面ですね。
左右の足で四股を踏む
せりあがったら右足、左足の順番で四股を踏みます。
ここは通常の四股踏みで結構です。
私は静かに足を下ろす四股踏みで行っていますね。
左足を踏んだあとは腰割りをします。
横綱土俵入りにはない動作ですがストレッチとトレーニングの締め
として意味合いもあります。
もっと詳しく四股踏みのやり方が知りたいという方はこちらの記事をどうぞ。
横綱土俵入りで強化できる動き
横綱土俵入りで強化できる肩関節周りと股関節周りの
動きついて説明します。
肩関節周り
肩関節周りの動きです。
「拍手を打つ」「両手を広げる」の動作について解説します。
拍手を打つ
拍手を打つ際は腕を大きく回します。
この動きでは三角筋、僧帽筋、僧帽筋、肩甲挙筋、菱形筋
などの筋肉が働きます。
また、これらの筋肉を動かすことで筋肉がほぐれて肩が正しい
位置に戻りやすくなり姿勢の改善が期待できます。
両手を広げる
両手を広げる動きでは肩甲骨が大きく動くますが
この時は直接肩甲骨を動かす筋肉だけではなく鎖骨を支点とする
鎖骨周辺の筋肉も働きます。
また、左右の掌を返す動きは重心移動、特に上半身の重心移動を
誘導する動きとなり、この動きに習熟するとスムーズな重心移動が
できるようになります。
股関節周り
股関節の動きです。
「四股を踏む」「せりあがり」について解説します。
四股を踏む
四股踏みではお尻やふくらはぎ太ももなどの下半身を中心とした筋肉も
もちろんですが、腸腰筋など深層筋(インナーマッスル)を鍛えることが出来ます。
また、これらの筋肉がほぐれると股関節が柔らかくなり、
骨盤のゆがみを整えることが出来ます。
せりあがり
せりあがりの動きでは股関節の外旋と内旋を繰り返します。
股関節の外旋には外旋六筋という筋肉が働きます。
この外旋六筋は大腿骨頭を骨盤の臼蓋に引き付ける役割りがあります。
股関節を安定させるんですね。
簡単にいえば太ももの骨の上部にあるボールを骨盤の受け皿にはめ込む働きを
します。
この外旋六筋がうまく働かないと股関節がグラグラと不安定になるとともに
これをカバーするために表層の筋肉(中殿筋など)、お尻周りの筋肉が働きだします。
これはパフォーマンスに悪影響を及ぼし、股関節痛につながる場合もあります。
せりあがりでは身体の深層部にある外旋六筋を活性化することが出来ます。
儀式・神事としての土俵入り
相撲は元々神事に由来しています。
取組前に塩をまくなども正に清めですよね。
土俵入りは神社や寺院を建立する際に行われた地鎮祭で行われていた「地踏みの儀式」
がルーツとされているそうです。
土俵入りの基本は、地を清め鎮める「四股」と「拍手」です。
いずれも神聖な所作で構成されていることが判りますね。
儀式・神事として捉えれば精神的な安定にもつながるのではないでしょうか。
まとめ
今回の記事では「横綱土俵入り」で肩甲骨や股関節を鍛える方法を紹介しました。
横綱土俵入りの中でも「拍手を打つ」から「四股を踏む」までの動作を用いた
トレーニング方法でしたね。
それぞれの動作では
拍手を打つ ⇒肩甲骨の動き
両手を広げる ⇒肩甲骨の動きと体重移動の連携
四股を踏んでからせりあがる ⇒股関節を外旋させる動き
左右の足で四股を踏む ⇒股関節や体幹
を強化することができます。
また、元来神事であった土俵入りの所作なので精神的な安定にも効果があります。
私がこの効果に気がついたのは、元横綱の方が「(横綱)土俵入りは良い鍛錬に
なるんだよ」と言っていたからです。
いろいろ調べ、自分でもやってみるとその効果に驚きました。
時間もそれほどかかりませんので是非とも試して頂きたいですね。
自分が横綱になった気分でやるのは結構楽しいですよ。
強度が高いのでご自身の体力に合わせて行ってくださいね。
最後まで読んで頂きありがとうございました。
この記事が皆様の身体創りの一助になれば幸いです。


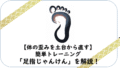
コメント